女性社員が管理職に昇進できない会社には、明文化されていない“風土”が深く関係しています。これは制度やルールには現れにくいものの、日々の職場の空気感や意思決定の中で無意識に機能しているため、非常に根が深く、変えるのが難しい側面があります。以下に、そのような会社の風土と原因、そして具体的な対策を詳しく解説します。
—
■ 1. 「男社会」の暗黙の前提が根付いている風土
● 風土と原因:
組織全体に「管理職とは男性が務めるもの」という暗黙の了解があるケースです。このような会社では、管理職は長時間労働が当然とされ、家庭よりも仕事を優先する「献身型」こそが理想の管理職とみなされています。
こうした前提があると、出産・育児と仕事を両立しようとする女性は昇進対象から無意識に外されがちです。また、「女性が管理職になると周囲が気を遣う」「部下がついてこないのでは」という根拠のない懸念もあり、上層部が登用をためらうこともあります。
● 対策:
経営陣自ら「管理職像の再定義」を行い、性別に関係ない多様なリーダー像を打ち出す
昇進・登用の決定に「性別」の影響が出ないよう、人事評価プロセスの透明化と基準の明確化を進める
成果や能力を重視する文化へ意識転換を図る啓発活動の実施
—
■ 2. 女性に対する「配慮」が逆にチャンスを奪っている風土
● 風土と原因:
「子育て中だから忙しいだろう」「転勤は無理だろう」「残業ができないはず」といった“善意の配慮”が、女性への挑戦や抜擢の機会を事前に奪ってしまうケースです。これが女性の「昇進意欲の低さ」「成長機会の不足」につながっていきます。
つまり、女性本人の意思を確認せずに周囲が勝手に判断し、「どうせ難しいだろう」と昇進の選択肢を与えない空気が蔓延してしまうのです。
● 対策:
配慮ではなく「選択の自由」を尊重し、昇進や異動の機会を性別問わず平等に提示する
上司によるキャリア面談や1on1で、本人の意欲や希望を定期的にヒアリングする仕組みをつくる
「家庭との両立を理由に昇進を辞退することが恥ずかしい」という空気を払拭する心理的安全性を確保
—
■ 3. 男性同士の非公式ネットワークに偏った意思決定
● 風土と原因:
意思決定や昇進の話が、正式な会議ではなく、飲み会やゴルフなどの非公式な場でなされるような文化では、男性社員だけがそうしたネットワークに参加しやすく、女性が疎外されがちです。
また、「○○君はあの上司に可愛がられてるから次は課長だな」というように、実績よりも“顔の見える関係性”が重視される職場では、女性社員はどうしても蚊帳の外になりやすいのです。
● 対策:
非公式な情報伝達や昇進ルートを是正し、制度としての「タレントマネジメント」を導入する
昇進候補者の選定を複数人で行う「タレント会議」の設置
キャリア開発におけるスポンサー制度(影響力のある管理職が後押しする仕組み)を女性にも広げる
—
■ 4. 管理職に就くメリットが女性に見えにくい風土
● 風土と原因:
「管理職=責任が重くなるだけで報われない」「プライベートが犠牲になる」というイメージが強い職場では、女性に限らず昇進を敬遠する人が増えますが、特に女性社員にとっては「二重負担(仕事と家庭)」のリスクが大きく映りがちです。
また、職場に女性管理職のロールモデルがいない場合、「自分もなれる」と思いにくく、キャリアの先が見えづらくなります。
● 対策:
管理職の働き方改革を進め、柔軟な勤務スタイルでもマネジメント可能な環境を整備
女性管理職の成功事例を社内で共有し、モデルケースを可視化
管理職としてのメリット(スキルアップ、裁量の大きさ、報酬など)を丁寧に伝える教育機会を設ける
—
■ 5. 経営層に多様性への無関心がある風土
● 風土と原因:
経営トップに「女性登用は単なるポリコレ(政治的正しさ)だ」と受け取られると、形だけの取り組みになり、本質的な改革が進みません。「女性を登用したら逆差別だ」といった声が経営層や管理職にある場合は、現状維持が優先されてしまいます。
また、「女性登用の必要性がビジネスとどう関係しているか」という視点が欠如していると、真剣に取り組まれません。
● 対策:
ダイバーシティが業績や企業価値向上に直結することを示すエビデンスを経営層に共有
トップマネジメントが定期的に女性社員と対話し、現場の課題を直接把握する仕組みを作る
役員報酬や評価にダイバーシティ指標の達成を連動させる
—
■ まとめ
女性が管理職に昇進できない背景には、単なる制度上の問題だけでなく、「女性には無理だろう」「管理職はこうあるべき」という思い込みや、善意の配慮が結果として壁になっていることが多くあります。
このような風土は一朝一夕に変わるものではありませんが、トップの本気の姿勢と、現場での意識改革、制度の整備を継続的に行うことで、少しずつ変化を促すことが可能です。女性自身のキャリア意識のサポートと並行して、組織の構造自体にメスを入れることが、最終的な鍵になります。
女性が管理職に昇進できない原因・いまだ蔓延する古い体質
 仕事
仕事

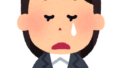
コメント