「Fラン大学」という言葉は、偏差値の低さや世間的評価を揶揄するために使われることが多く、蔑視や差別的なニュアンスを含みやすい表現です。しかしながら、そのようなレッテル貼りが本質的に無意味であるという点を、いくつかの観点から詳しく解説します。
■ 1. 「学歴=すべて」ではない現代社会
現代の日本社会では、かつてに比べて学歴だけでは測れない力が求められています。例えば:
- 実務経験やスキル
- コミュニケーション能力
- 課題解決力や創造力
- 継続的に学び成長する姿勢
こうした力は、偏差値とはまったく関係ありません。どこの大学に通っていたかより、「今どれだけ努力しているか」が評価される社会に少しずつシフトしているのです。
■ 2. 大学で何をしたかが重要
Fランと揶揄される大学に通っていたとしても、
- サークル活動やボランティアでリーダーシップを発揮
- アルバイトで社会経験を積む
- 独学で資格取得やプログラミングを学ぶ
- 起業やフリーランスとして実績を積む
など、大学生活の内容や行動次第で評価はまったく変わります。
実際に、名も知られていない大学から有名企業に入ったり、起業して成功する人も珍しくありません。つまり、「どこにいたか」より「そこで何をしたか」が重要です。
■ 3. レッテルで人を判断するのは恥ずべき態度
Fランという言葉を使って他人を蔑む行為は、以下のような点で問題があります:
- 他人の努力や背景を一切見ようとしない
- 一面的な基準(偏差値)で人を評価している
- 自分の優越感を保つためのマウントである場合が多い
- 本質を見ずに差別するという、思考の浅さが露呈している
こうした行為は、相手の尊厳を傷つけるだけでなく、自分の品位も下げる行動です。
■ 4. 本当に大切なのは「今」と「これから」
仮に大学受験で納得いく結果が出なかったとしても、それは人生の一部でしかありません。むしろ、
- 今、どんなことを学び、行動しているか
- 将来、どんな価値を生み出したいのか
といった**「これからの積み重ね」こそが、その人の本当の評価基準**になります。
■ まとめ:本人の努力が何よりの力になる
Fラン大学かどうかというのは、社会的評価の一側面に過ぎません。それを「汚点」と見るかどうかは本人の価値観と努力次第。他人が軽々しくバカにするようなものではありません。
むしろ、そこから努力し、成長し続ける人こそ、本当にかっこいい存在です。
大学の名前ではなく、人間としての行動、姿勢、思考、成果で評価されることを、忘れてはいけません。レッテルで人を見下すのではなく、真の実力を見抜ける目を持つことこそ、大人としてのマナーといえるでしょう。

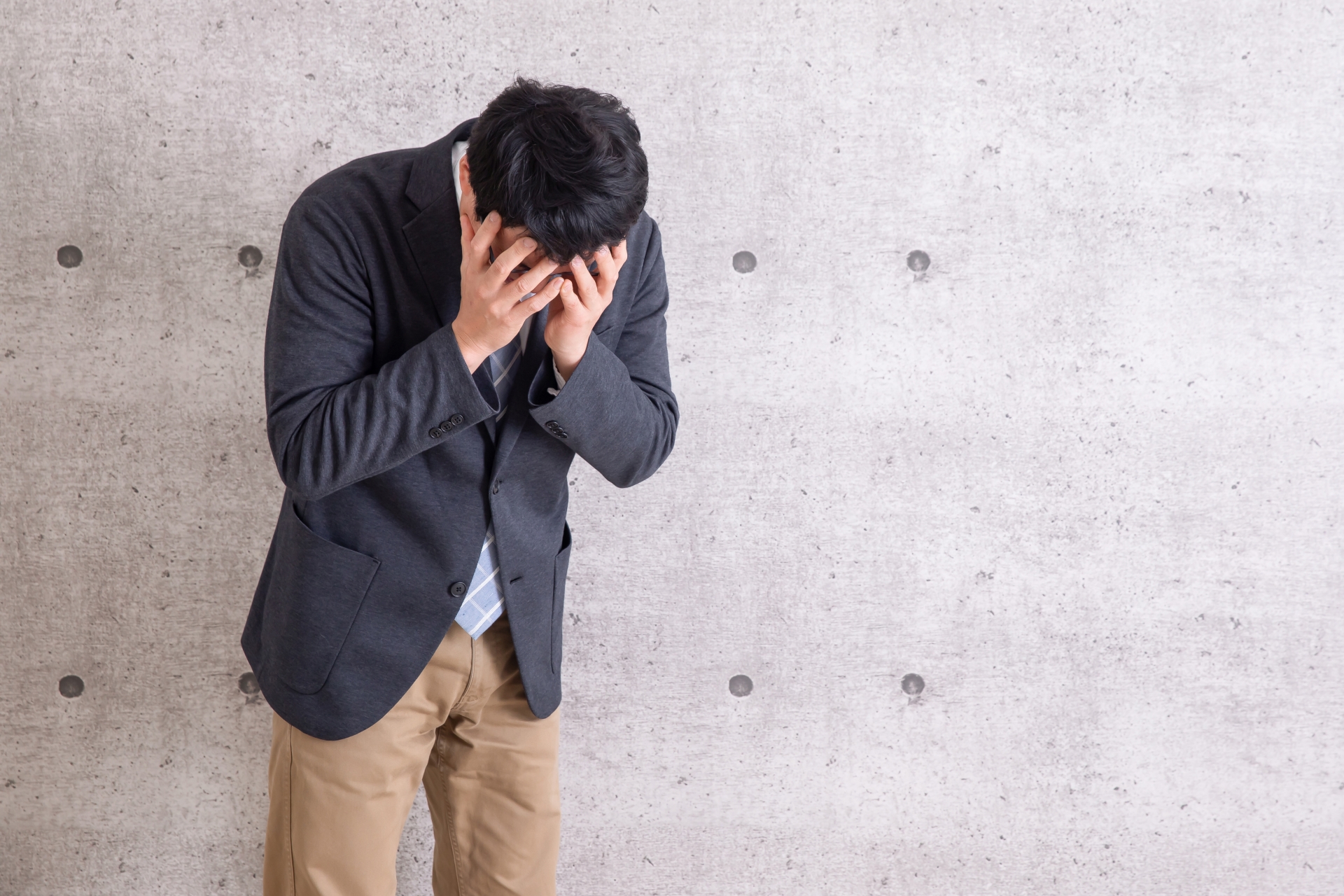


コメント