カルビーの「じゃがりこ」を含む多くのスナック菓子の価格は、一度上がると値下がりすることがあまり考えにくいのには、いくつかの経済的要因があります。以下の理由を詳しく解説します。
1. 原材料費の高騰とその定着
じゃがりこの主原料であるじゃがいも、小麦粉、植物油などの価格は、世界的な供給状況や天候、物流コストの影響を受けて上昇しています。
じゃがいも: 日本国内の生産量は限られており、天候不順による収穫量の減少や、輸送コストの上昇が影響を及ぼします。
小麦粉: 小麦は輸入品が多く、円安や国際情勢の影響で価格が上昇しやすいです。
植物油: 食用油は特に世界的な供給不足や国際的な価格高騰の影響を受け、安定した価格に戻るのが難しくなっています。
このように、原材料のコストが高騰したまま安定すると、一時的な値上げではなく「新しい価格基準」として定着してしまいます。そのため、以前の価格に戻る可能性は低いのです。
2. 人件費・物流コストの上昇
人件費: 日本国内では最低賃金が年々上昇しており、工場の製造コストや流通コストが増加しています。特に食品業界では人手不足が深刻で、労働者の確保に高いコストがかかります。
物流費: 燃料価格の高騰や、物流業界の「2024年問題」により、輸送コストも増加傾向にあります。
これらの要因は一時的なものではなく、継続的に企業のコスト負担を増やしているため、価格を下げる余裕が生まれにくいのです。
3. 小売価格の「値下げ圧力」が弱い
一般的に、商品価格は競争が激しいと値下げしやすくなります。しかし、じゃがりこはブランド力が高く、一定の需要が見込める商品であるため、メーカー側が安易に値下げする必要がありません。
根強いファン: じゃがりこは長年の人気商品であり、値段が多少上がっても一定数の消費者は購入を続けます。
競合との関係: 他のスナック菓子と比較しても差別化ができており、価格競争がそれほど激しくありません。
また、スーパーやコンビニなどの小売業者も、仕入れ価格が上昇すると販売価格を下げにくくなり、「安売りをする余裕がなくなる」という状況が生まれます。
4. 過去の値上げ傾向とその定着
カルビーはこれまでにも原材料費や物流費の上昇を理由に段階的な値上げを実施してきました。
例えば、過去には内容量を減らす「実質値上げ(ステルス値上げ)」が行われ、それでもコストが厳しくなると正式に価格改定(値上げ)に踏み切っています。
こうした値上げが定着すると、企業側も「新しい価格設定で利益を確保する体制」に移行するため、安易に値下げすることはありません。
5. 価格を下げることのデメリット
一度値上げした商品の価格を下げると、以下のような問題が発生します。
「値下げ待ち」の消費者が増える: 価格が下がることが期待されると、逆にすぐに買わずに待つ人が増え、売上が安定しなくなります。
ブランド価値の低下: 高品質なイメージがある商品を値下げすると、「安くしないと売れないのでは?」という印象を与えてしまう可能性があります。
そのため、メーカーは値上げをしても、よほどの事情がない限り値下げはしない方針を取りやすくなります。
結論
カルビーのじゃがりこが一度値上げした後に値下がりすることが考えにくいのは、原材料費や人件費、物流コストの上昇が長期的に続いていることに加え、ブランド力の高さ、価格競争の弱さ、企業戦略が影響しているためです。
過去の事例を見ても、食品業界では値上げが定着しやすく、一度上がった価格が元に戻ることはほぼありません。今後も、内容量の調整や新しいパッケージ戦略などでコスト管理を行う可能性はありますが、「じゃがりこが値下がりする」ということは非常に起こりにくいでしょう。
【円高】じゃがりこは今後また安くなる?【値下がり】
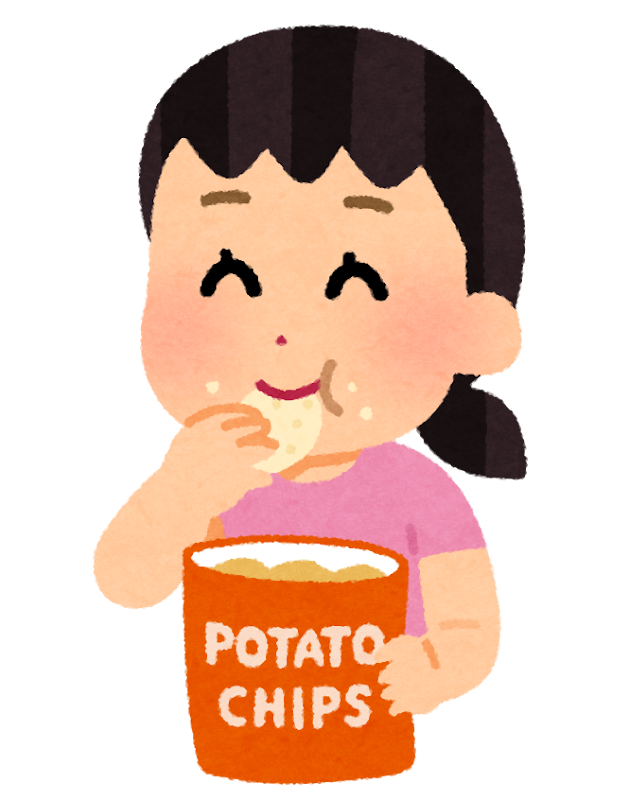 ニュース
ニュース

コメント